目次
ミツバチの巣が六角形の理由は?
なぜ正方形でも三角形でもなく六角形なのか。
じつは材料(蜜ろう)を最小限にして最大のスペースをつくれる形だから。しかも隙間もできません。
この六角形の効率性は材料力学や航空宇宙工学でも最強と実証済みで、「ハニカム構造」として飛行機や建材に使われています。
おもしろいのは、ミツバチたちは最初から“六角形”を狙ってないこと。最初は丸い部屋を並べていて、温められた蝋が押し合う力で自然に六角形になっていくんだそうです。自然が勝手に導く“機能美”。そしてその形を、はるか昔から自然が選んできた“最適解”として人間が科学で確認して真似しているって、ちょっと不思議で面白いですよね。
ボールペンの「キャップ穴」は安全設計
最近はフリクションボールペンなどノック式が主流になり、キャップ付きボールペン自体あまり見かけなくなりましたが…
実はあのキャップのてっぺんに空いている一見なんでもない小さな穴、じつは命を守る工夫。
誤って飲み込んだときに、完全に気道をふさがず空気が通るように設けられた“通気穴”です。国際基準(ISO)にも準拠していて、見えないところで守ってくれているデザインだそうです。
お札に“ざらつき”があるのはなぜ?
本物かどうかを“目じゃなく指で”見分けられるように作られているから。
偽造防止だけでなく、視覚に障害のある方も識別できるように券種ごとに違う凹凸マークが施されています。
見えないやさしさが織り込まれている触覚デザインです。
新紙幣では「すかし」に加え、傾けると文字や数字が浮かぶ「潜像模様」も仕込まれています(こちらは高度な偽造防止技術)。
また、額面数字を大きくし誰にでも見やすいUD(ユニバーサルデザイン)フォントが取り入れられました。ただ「太すぎて安っぽく見える」「慣れない形で読みにくい」といった声も一部で出ていました💦
バナナの“黄色いシール”にはブランド戦略が詰まっている
バナナに貼られた小さなシール、ただのラベルじゃありません。
「ブランドを持たない果物」に個性と価値を与えるマーケティングツールです。
袋や箱でブランドを出せないため、シール1枚で「どこのブランドか」「高級かお手頃か」を印象づける必要があります。
キャラクターや商品名でブランド認知を促すなど、小さなシールにも戦略が詰まっています。
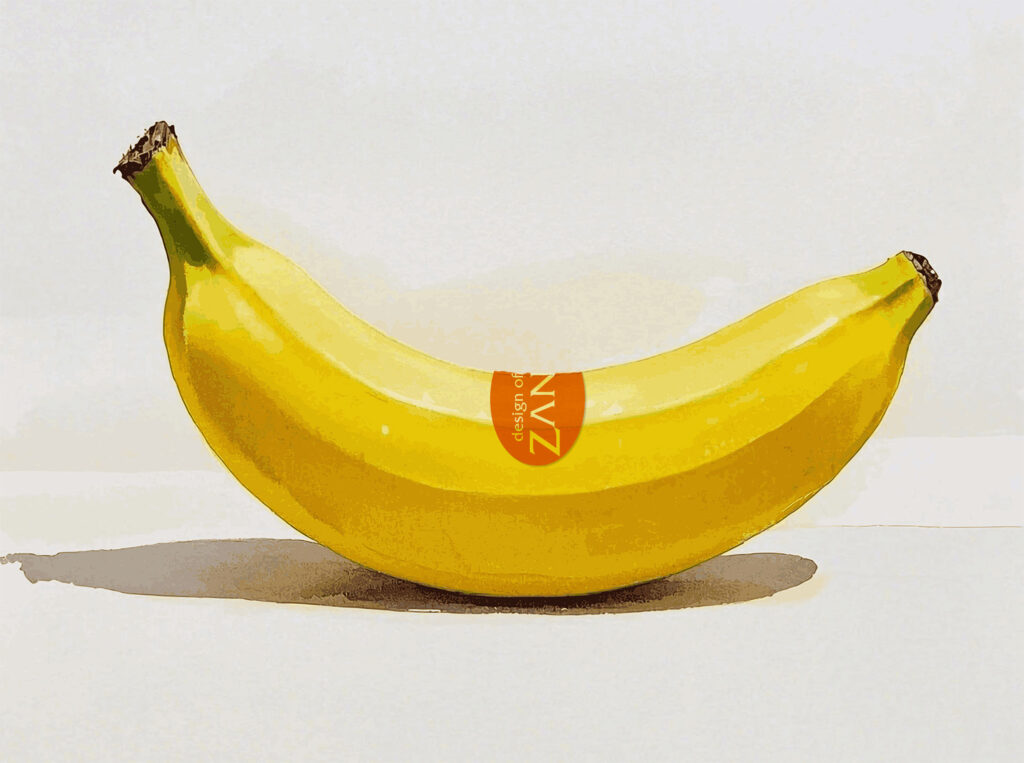
歩道の「点字ブロック」にもデザインの工夫
駅や歩道にある黄色い「点字ブロック」に、実は“誘導用”と“注意喚起用”で形が違います!
・線状の突起(バーが何本も平行に並んでいる)=進む方向を示す「誘導ブロック」
→ 駅構内や歩道など、足裏で“まっすぐ進む”ことを知らせます。
・点状の突起(丸いポチポチが碁盤目状に並んでいる)=段差や交差点を知らせる「警告ブロック」
→ 横断歩道の手前や階段・ホーム端などで、“ここから注意”を知らせます。
さらにブロックの黄色には意味があります。視覚障害のある人にとって見つけやすい色であると同時に、周囲に「ここは視覚障害者が通るかも」と知らせるサインにもなっています。
形(バーか点か)や触感と合わせて情報を伝える、まさに“ユニバーサルデザイン”の好例です。
まだまだありそうな隠されたデザインの常識、知っている方はぜひ教えてください。

