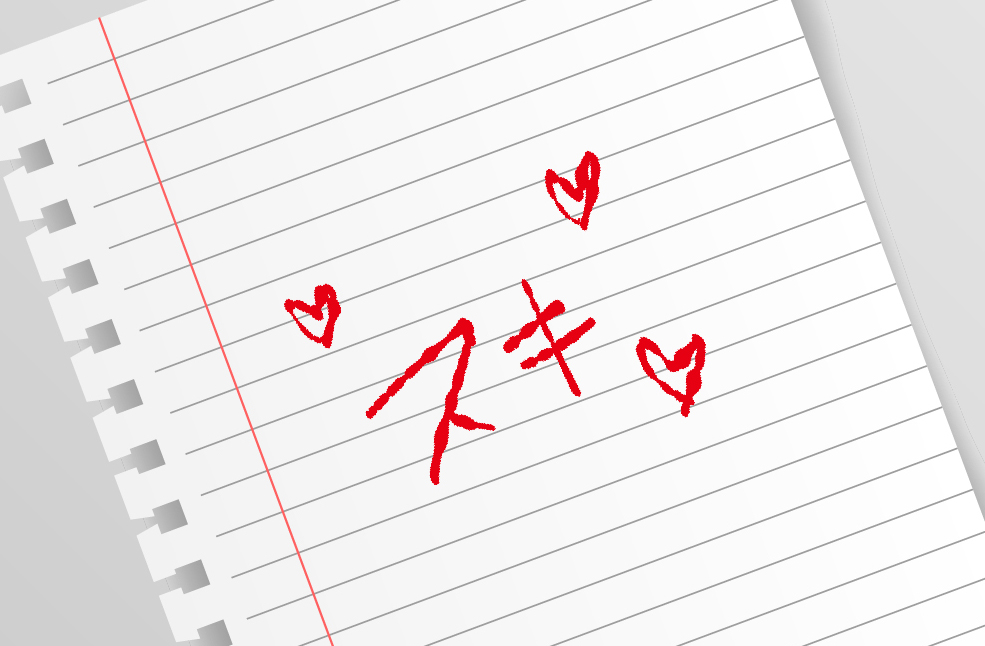前回は、自然界や身の回りにある“デザインの常識”をサラッとご紹介しましたが、
今回はその中でも「これ、なんでこうなってるの?」という理由をもう少し突っ込んでお伝えしていきたいと思います。
■ ノートの“赤い縦線”は何のため?
→ 実は、先生や編集者のために引かれていた!
学生時代、当たり前のように使っていたノートの左端の赤い縦線。
実はあれ、本文との余白というより、「赤ペンでコメントを書きやすくするための補助線」がルーツ。
もともとは採点や校正をする人のための“視認性の工夫”だったんですね。
今では見出しを揃えたり、マーカーの目安にしたりと用途も広がっていますが、
「読む人・チェックする人のことを考えた設計」だったというのは、意外と知られていません。
■ 文庫本のサイズは何を基準にしているの?
→ 文庫本サイズは“着物の袖に入る”大きさだった!
日本の文庫本のサイズ(A6)は、実は江戸時代の和本のサイズ感を引き継いでいると言われています。
その理由のひとつが、「着物の袖や懐にすっと入れて持ち運べるサイズだから」
今でも、通勤電車で片手で読める、カバンにすっきり入るなど、
移動中に読むための“携帯性”がちゃんと考えられた設計になっています。
最近はスマホで読む人も増えましたが、文庫本の心地よさって、やっぱり魅力的ですよね。
■ エレベーターの「閉」ボタンがわざと効きにくくされている?
→ 実は“やさしさ”からくる設計だった!
「閉まるボタン押したのに、全然閉まらないなぁ…」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
実はそれ、わざと反応が遅くなるように設計されていることがあるんです。
高齢の方や体の不自由な方、子どもなどが乗り遅れないよう、
あえて“素早く閉まらないように”しているという、さりげない配慮。
「すぐ閉まらない=やさしさ」なんですね。
※もちろん、すべてのエレベーターがそうというわけではありません。

普段何気なく使っているものにも、小さな理由や優しさがデザインされている。
そんな視点でモノを眺めると、少しだけ面白く見えてきます。
他にも「えっ、そんな理由が?」と思うようなデザインはたくさんあるので、
次回もまた、身近な例をピックアップしてお届けしていきますね。