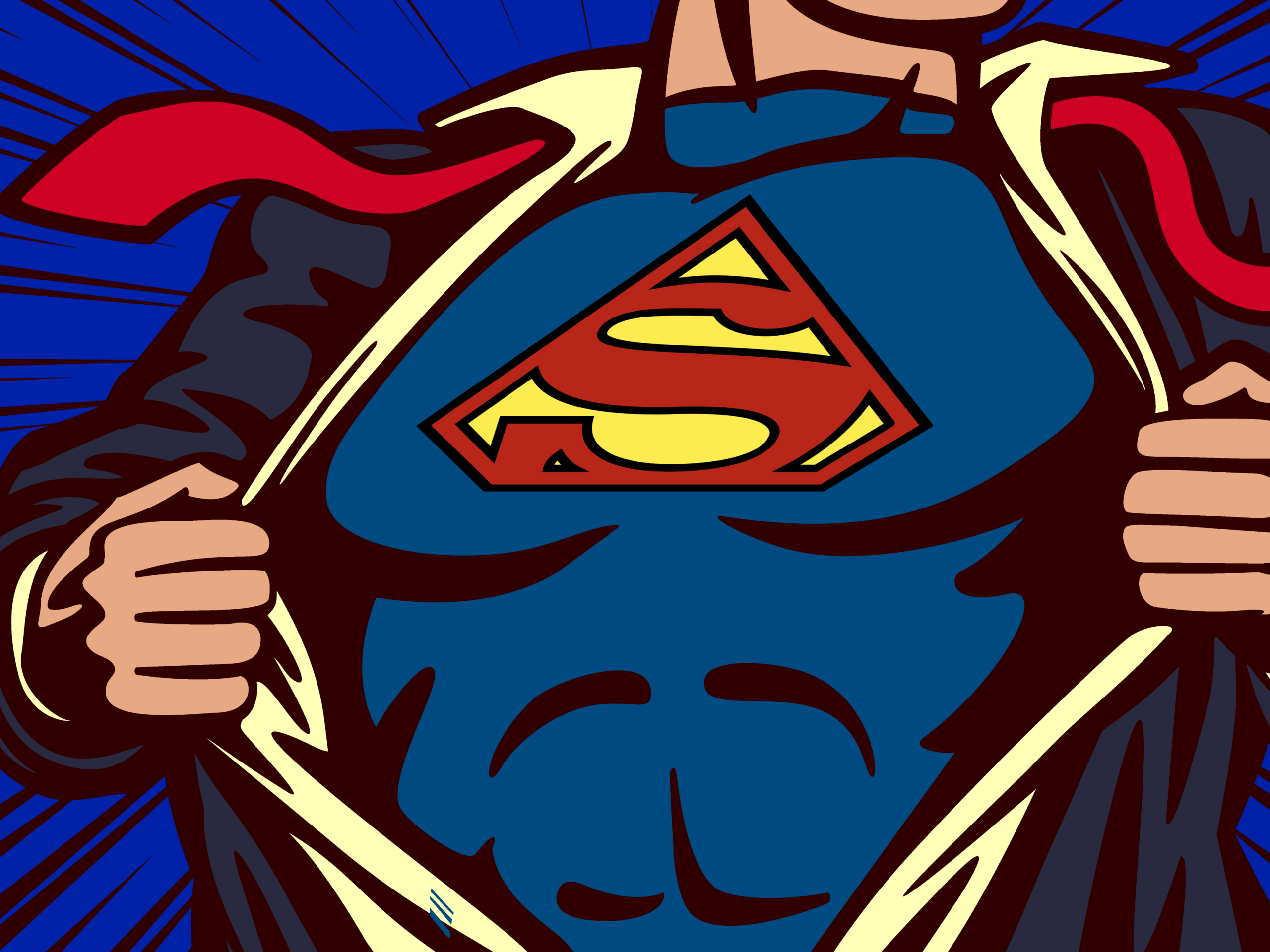少し前に「色には意味がある」というテーマでお届けしましたが、
今回は“色”だけではなく、形や重心、素材感などにも意味があるというお話です。
それらがどうやって人の感じ方に影響を与え、デザインに活かされているのか、身近な事例からいくつかご紹介します。
目次
動物の模様は“敵の目をごまかす”ため
ゼブラの白黒縞模様は「目立つ」ではなく「動いてるときに目がチカチカして狙いが定まらない」という“錯視”効果。
▶ 視覚のトリックを使った広告やパターンデザインのヒントに。
道路標識は“逆三角形”で意味が変わる?
同じ赤い縁でも、「○」と「△」では伝わる意味が違う(進入禁止と徐行)。
▶ 形と色の組み合わせが、直感的に伝える「記号化デザイン」の典型例。
動物の目は“正面”と“横”で違う意味を持つ
肉食動物は目が正面、草食動物は目が横にあります。これは「見る目的=生存戦略」の違いによるもの。
▶ ロゴやキャラの“目線の向き”にも応用できる話。
人は「左から右」へ流れる動きに安心を感じる?
私たちは文字や時間を“左→右”で認識するため、動きや矢印もこの方向だと「自然」だと感じやすい。
▶ Webデザインやプレゼン資料でのアニメーション演出にも活用可能。
切手や硬貨に隠されたデザインの“重心”
硬貨や切手などの小さなデザインは、視線がぶれない“中央重心”の設計になっていることが多い。
▶ ミニマルな空間でも“視認性を保つ工夫”がされている。
パスワード入力欄の「●●●」は、実は古い慣習
本当はセキュリティよりも“操作中”であることを示すUIデザインの名残。
▶ 最近は「表示する/しない」を切り替えられる理由も、ユーザビリティの変化から。
おにぎりの「三角形」にも機能性がある?
実は持ちやすさ・視覚的な安定・包装の効率すべてを満たす形。
▶ “形=デザイン=売りやすさ”の一体化。
コーヒーカップの「フタの形状」にも特許がある
飲みやすさ・香りの広がり・こぼれにくさなどを極限まで設計。
▶ コンビニで何気なく使うあのフタも“飲み心地”という体験を設計したデザイン。
なぜプリンの容器は“底がすぼんでいる”のか?
実は「ひっくり返しやすいように」「中身がきれいに出るように」設計されている。
▶ 見た目ではなく“裏返す動作”まで想定したデザイン。
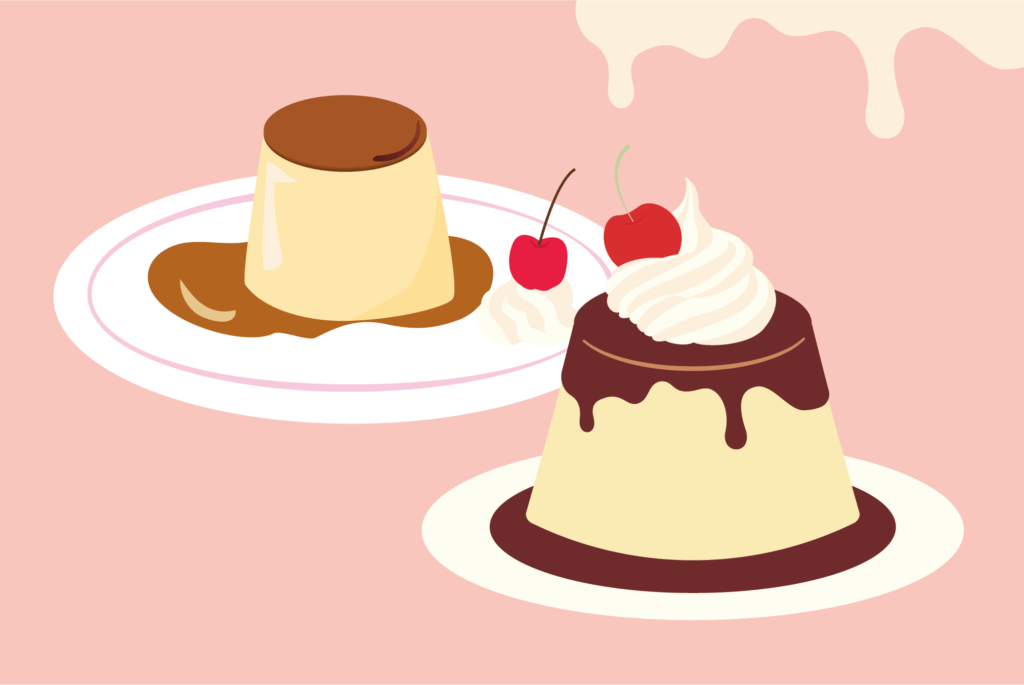
一部の電車の“つり革の高さ”が違う理由
小柄な人や子ども、車椅子ユーザーでもつかめるように、あえて高さをバラバラに。
▶ “均一=親切”ではない、多様性に配慮したデザイン。
ちょっとボリュームが多くなってしまったので、続きはまた次回にお届けしたいと思います。